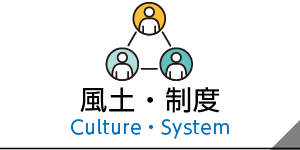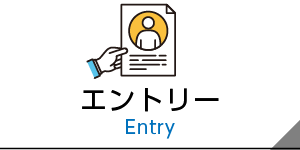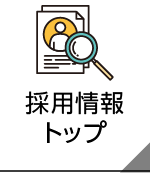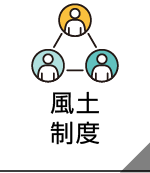職員
インタビュー

コンサルティング統括事業部
生産・業務改革コンサルティング部
K.K
4年前の2020年、コロナ禍に転職、中産連に入られましたが、
その前はどのようなお仕事をされていましたか
建材メーカーで生産設備の開発設計に携わっていました。工作機械メーカーでの経験もあり、この分野が私の専門です。さらに、前職在任中に中小企業診断士を取得しました。
当時からコンサルタント志望だったのですか
いえ、当時は職業として、という動機よりも、自分の専門性をさらに高めるために、企業を全体から、経営の観点で理解したい、という気持ちから挑戦していました。結果的には、現在の生業となりましたが。
企業人からコンサルタントへの転身ですが、
成り立ての頃を振り返るといかがですか
やはり最初は「お客様から受け容れてもらえるだろうか」という不安はありました。所詮私たちは「外の人」ですから、プレッシャーはありました。
どういうタイミングで、そうした不安から解放されましたか
私の場合、変化のきっかけは、あるお客様をひとりで任されたことでした。基本、新人の頃は上司や先輩と1チームで、診断、指導案・改善案づくり、提案、実行となるんですが、あるとき、チームで診断した後「ここからはひとりでやってみて」ということになったんです。そのときの指導テーマや、クライアントの業種、相性など、そのケースでの上司の見立てがあったのだと思います。いざ一人で任されるとなると、かなり動揺しました。あまり顔に出ないタイプですけど(笑)。
ひとりで担当してみてどうでしたか
こちらが新人であることはお客様には関係ありませんから、とにかく全力でやってみようという思いで毎回臨んでいました。その中で、早い段階で『手応え』というか、極めてベーシックなことでも役立つ場面があるなぁ、ということを実感しました。自分では「こんなことは当たり前」と思っていたようなことでも、活用すべきところでしっかり使えるよう指導することで、十分レベルアップさせることができるな、と。これは嬉しい発見でしたね。 その会社には今でも継続して支援をしていますが、今から思うと、「一方的に高度な知見を伝える」スタイルよりも、従業員の方々と一緒になってやってくれるタイプを望まれていたのだと思います。現場で実際に従業員の方々と対話を重ねる中で、それを感じることができました。このスタイルが信頼関係を築く大きな要因になったのだと思います。
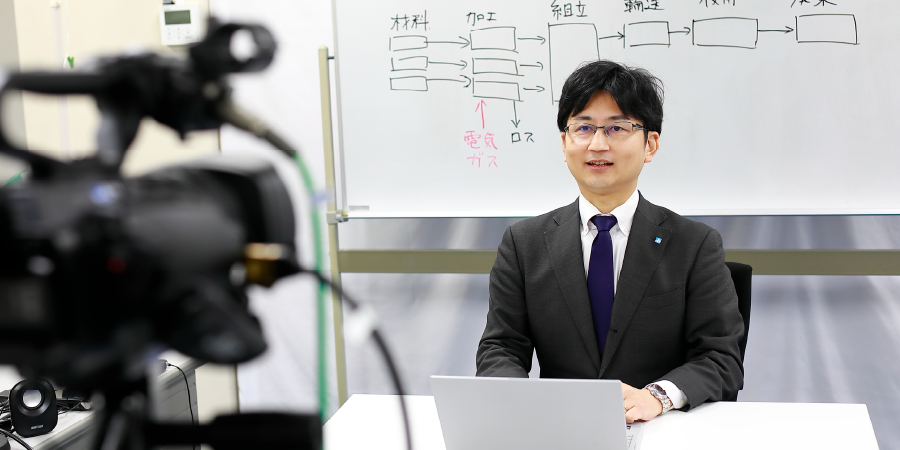
長いお付き合いになっている、ということですね
そうですね。当初の生産性向上、原価低減、5S推進などは、オーソドックスなテーマであり腰を据えてやるものなので、今でもレベルを上げながら継続していますが、付き合いが長くなって相手のことがわかってくると、それ以外の問題も見えてきて、年度の節目ごとに「こういうこともやるべき」という提案もします。また、先方からまったく異なる課題、たとえば採用や人事評価などを投げかけられるときもあります。私の専門外、とわかっていても敢えてご相談いただけるときは、頼りにされていることを感じ、嬉しいです。本来、餅は餅屋で、そのテーマに精通した人にあたるとか、こちらもリファーするとか、そうすべきかも知れませんが、信頼されていることに応えたい、という気持ちが勝り、一生懸命調べたり勉強したりしています。おかげでお客様からは評価をいただいていますが、こうして専門の領域を広げ、経験値を上げていけることは、お客様に育ててもらっていることなんだな、と痛感しています。
連盟が力を入れているカーボンニュートラル(以下:CN)の
プロジェクトにも参加していますね
コンサルタントだけではなく、企画職の若手メンバーとも、同じ目的の下で活動し、交流できるいい経験の場になっています。それぞれの立場でいろいろチャレンジして持ち寄り、皆で検討をしています。コンサルタントとしては、実際の支援現場で試行できることに意義を見出しています。このようなプロジェクトの良さは、試したことを共有して広めてもらうことだと思っています。中産連がCNに取り組む意義、他との差別化要素としては、たとえば、どこも取り組む「消費電力量の測定」ですが、当然、中産連でもやります。しかし私たちは、測定した後の対策提案を、現場の状況をよく理解し、現場密着・現場発信でできることが強みだと自負しています。生産現場をよく知る中産連ならではの特長を今後も打ち出していきたいと思いますし、それこそが私たち中産連がやる意義だと思っています。
コンサルタントの立場で、
中産連という職場をどのように感じていますか
基本的に、ある程度の自由が確保されており、自己責任のもとで自分のスタイルで取り組める環境だと思います。もちろん上司や先輩方にはフォローしていただけます。時間を新しいテーマの研究に充てることができ、専門知識を深められます。ただ、何でも手を出せば良いわけではなく、専門性という芯をぶらさず、ポイントを押さえながら拡張していくことは重要だと思います。分野を限定しないことは、自らの可能性を大きく広げることになるし、好奇心が強い自分には合っていると感じています。
今後力を入れていきたいことはありますか
さらに組織として動けるようにしていきたいです。情報の共有度を上げるコミュニケーションを積極的に行い、コンサルタント個々のレベルアップ、相乗効果を生み出せるような場作りに力を入れたいですね。また、自身の技術者としての専門性をさらに高めて、設計者の育成を体系化して実践してみたいと思っています。
これを読んでいる方に一言
ご自身の専門分野については、まずしっかりと確立していただければと思います。その上で、会社全体を見ること、全体の収益を上げるというチャレンジに意欲を持って取り組める人と一緒に働きたいですね。お待ちしています。